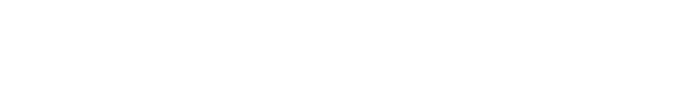ナミビア派遣報告 ―基盤研究Sの組織体制づくり―
京都大学大学院
アジア・アフリカ地域研究研究科・教授
高田 明

令和6年10月18日から11月3日にかけて,おもにナミビアのナミビア大学,JICAナミビア・オフィス,在ナミビア日本大使館,オシャナ村,エンドベ村,オナンジョコエ医療博物館,ナミビア国立資料館・図書館などを訪問し,本プロジェクトに関する研究打ち合わせ,資料収集,現地調査などを行った.今回は短期の滞在であり,とくに直近の南部アフリカ滞在(令和6年8月1日から9月3日)においてやり残した基盤研究S「アフリカ狩猟採集民・農牧民のコンタクトゾーンにおける子育ての生態学的未来構築」を推進していくための組織体制づくりに力を入れた.
ナミビアに到着してから,首都のウインドフックで本プロジェクトのカウンターパートであるナミビア大学を訪問し,共同研究者であるRomie Nghitevelekwa講師,Martha Akawa上級講師らとナミビアの狩猟採集民・農牧民のコンタクトゾーンに関する打ち合わせを行うとともにこれに関する資料収集を行った(写真1).Nghitevelekwa講師とAkawa上級講師は最近ナミビア北中部において気候変動に応じた在来の生態学的知識(Indigenous Ecological Knowledge)の活用についての研究を進めており,本研究プロジェクトとの関連でも同地域の狩猟採集民・農牧民のコンタクトゾーンにおけるそうした在来知の(再)創造や活用について共同研究を進めていくことを検討している.
続いてJICAナミビア・オフィスを訪問し,本プロジェクトの概要やこれまでの活動について星野明彦所長らに説明した上で,今後の活動協力の可能性について懇談を行った.JICAには,草の根技術協力事業など,現地の社会に根ざした開発事業を支援する枠組みが整っており,こうした活動は本プロジェクトで模索しつつある在来知の再活性化や職業訓練についてのアクション・リサーチとも親和性が高いことを再認識した.在来の知識や社会組織を活用することは,地域住人が高いモチベーションを持って開発事業に参画するだけでなく,そうした開発事業を成功に導くためにも不可欠であることについて豊富な実例と共に語り合い,楽しく有意義な時間であった.
さらに,在ナミビア日本大使館の西牧久雄大使らと昼食を共にしながら,懇談を行った.国際的な経験や政府高官との交流が豊富な西牧大使からは,ナミビアの政財界の現状について貴重なお話を聞くことができた.また報告者のこれまでの調査研究の経験をまじえつつ,ナミビアの歴史的な特徴や少数民族をめぐる社会状況などについて,大変興味深い意見交換を行うことができた.
その後,ナミビア北中部に移動し,同地の狩猟採集民として知られるクンやアコエが多く住むオコンゴ地区のオシャナ村,エンドベ村を短期訪問した.オシャナ村では,住人から,生業活動に関わる現状などについて聞き取りを行った.とくに近年は政府の開発事業が十分機能しておらず,雨期の初めに畑地を耕起するためのトラクターが調達できないなどの問題があるということだった.得られた知見は,今後のアクション・リサーチに活かしていきたい.エンドベ村では,幼児向けの幼稚園を訪問した(写真2).またヘッドマンのWalde Mdatipo氏を訪問し,村の歴史や現在の問題点について意見交換を行った.宣教団が20世紀の半ばにまだ未開拓だったこの地域を訪れ,水が豊富(エンドベはwater panという意味)なことから村を拓いていったことなど,興味深く拝聴した.その後,村の小・中学校を訪問し,生徒や先生と懇談の機会を持った.エンドベ村の小・中学校では狩猟採集民サンと農牧民オバンボの子どもたちが共に学校に通っており,本プロジェクトのコンタクトゾーンの観点からも注目される.

その後,ナミビアルター派福音教会(ELCIN)の本部が置かれているオニパに移動した.オニパには,ELCINが開設・運営の主体となり,その後独立したオナンジョコエ病院があり,同病院には,その歴史的な貢献を紹介したり,オナンジョコエ病院の活動資料を保管したりしているオナンジョコエ医療博物館が付設されている.ここでは,前回の滞在でも調査に協力していただいたKleopas Nghikefelwa氏と活動を共にした.Nghikefelwa氏とは,彼の父親であり,ELCINの言語学者としてサンの識字教育に携わっていた故Sakaria Nghikefelwa氏の活動についての大変興味深い聞き取りや資料収集を行うことができた.その結果は,今後Nghikefelwa氏と報告者の共著論文としてまとめていく予定である.

またオニパでは,オナンジョコエ病院で働く Wilhelm Hainane牧師が教会と病院の活動の深い関わりについて説明してくださった.ELCINは,植民地期からこの地域への布教のみならずナミビアの解放運動や独立後の国家建設に関して多面的な貢献を行ってきた.Hainane牧師は,報告者の指導院生であり,ELCINの活動について調査を行っている渡邉麻友さんのホストファミリーも務めてくださっている.同氏らとの今後の交流を通じてELCINのユニークな活動史についてさらに多く学ぶことができることを確信した.
紙幅の制限のため十分に述べることはできないが,その後も,ナミビア北中部の市街地やウインドフックにおいて,本プロジェクトの関係者と研究打ち合わせを行ったり,資料収集を進めたりした.以上を通じて,基盤研究Sを推進していくための組織体制づくりに大きく貢献できたと考えている.これを可能にしてくれた関係諸機関や人々に感謝したい.