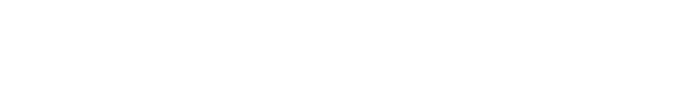インタビュアー:高田明、山本始乃
インタビュー実施日:2024年7月12日
研究内容について
山本:研究内容について教えてください。
川島:主にヘルス・コミュニケーションで会話分析を使って、色んな医療現場の分析をやっています。救命やプライマリーケア、遺伝カウンセリングなど若干シリアスな、交渉が必要になるような場面の研究をしています。子どもの研究も行っていて、高田先生と一緒に日本の子育てデータの分析をさせていただいてます。

バーデルスキー(以下マット):会話分析と言語社会化を組み合わせた形で親子の会話やペア同士の会話、家庭だけではなく学校、保育所とか幼稚園とかでデータを収集しています。

基盤Sとの関わりについて
山本:子どもや会話、相互行為といった部分で共通点があると思うのですが、基盤Sとの関わりについて教えてください。
川島:今までの子ども-養育者の関わりの中で、マットとも(この共同研究とは)違う場面で着目してたのがstory telling という場面です。物語を語るということが様々な場面でどのようなことを意味するのかというような分析を今までは日本の子どもや他の場面で行いました。以前、マットとは全米日系博物館(Japanese American Museum)における日系の方のstory tellingで、ガイドツアーでどういう語りが行われるかを一緒に研究させていただきました。そうした物語の構築と基盤Sで行われている紙芝居のプロジェクトは将来的に関わってくるのではないかと思っています。(狩猟採集社会で行われている紙芝居の)データを楽しみに待っています。story tellingって色んな場面で行われる活動です。私も他の医療データ等で、何かを説明したり、分かりやすく伝えたりというようなことが、「こういう風にしてね」と言うだけでなく、それを物語に埋め込むみたいなことがどういう意味を持つのかとか、例を出して説明を分かりやすくする時にその例がどういう意味を持つのかみたいなことを、制度的な会話の中でも研究しています。そういった取組が今後、基盤Sの研究に役立てばいいなと思っています。
(中略)
高田:story tellingの話で、人類学の民話の語り(Folktale)も昔からのテーマです。紙芝居でもそういう民話を取り上げているので、紙芝居的にしたものとか、昔ながらの焚火を囲んでおじいさんが語ったものとか、色んなバージョンが収録できていて、すごく古い問題意識を新しい手法で研究できそうだなというのは感じています。
マット:今は外での散歩についても研究しています。外に行って子どもたちが動いている鳥とか地域の猫、あるいは動いていない自動販売機とか自分にとっては意味のある、色々気付いたものを指差す。自分から気付きを開始して、誰かの注意を引いて、それに対してコメントしてもらう。もし無視されたりする場合、「先生、先生!」と呼んだり、声を大きくしたりしてもう一回返答を追求する。一つの方法論にも関連するかもしれないのですが、(これまでの)多くの制度的な場面での研究は建物の中で行われてきました。一方、基盤Sや私のこれまでの研究のいくつかは、外に行ってジャングルの中での子どもたちの冒険とかペア同士の会話とかそういったものを観察します。そういう所が一番関連しているのではないかと思います。さらに、言葉だけではなく、対象者が何を見ているのかとかマルチモーダルな会話分析の問題とか、他にも何人かの研究者がやっているような観点からそれを分析していくことにも意味があるのではないかと思っています。それは研究者にとってすごく大変なことです、付いて行かなきゃいけないので。子どもたちが今何をしてるのか、自分の身を守りながらこけたりとかしないように、カメラをもちながらやっています。本当に危険なので、2人でやった方が安全だろうということもあります。僕もこけたことがあります。
川島:マットがやってるの?
マット:僕はコロナ前のデータですが、4年前に大学の近くで撮ってました。もう一つは、日本語が母語の子どもたちだけでなく、日本語を第二言語として使用している子どもたちの研究です。子どもたちは本当に日本語がゼロなので自分の母語で言葉を言ったりしています。例えば、散歩中にバングラデシュ語で「ガリガリ」と言っていて、誰も最初はガリが何か分からないけども、1~2週間経っていくとガリが車だってことを皆が認識してて、同じように他の子どもたちも「ガリガリ」って言う。そしていつの間にかガリが日本語の車に変化されるんだけど、最初は自分の母語でも、自分と相手の離れたものでも注意を引く。トマセロがやっているような(中略)ジョイントアテンションのエコロジカルシステムと、もうひとつの3つの視点が関連しているかどうかは分からないけども、興味ある所はそこです。散歩は移動していくので、だんだんと環境が変わっていく。家の中だったら限定されているけど、移動すると目に入ってくるものも変わってくるし、遠い所にあるものから近い所にあるもの、動いているものとか子どもたちは興味あるし気付く。カラスとかいきなり指さして、「あ、カラスいるんだ」とか。だから言葉無くても参加できる、参与できるような。
川島:CCIのデータでも散歩の妊婦さんと、お兄ちゃんとかお姉ちゃんと散歩に行ったりするシーンがあって、ああいう時に気付きの発話から始まって経験語りみたいなのになるようなところとかすごく面白いなって思う。
マット:そうなんだよね。あとそういうのもすごく、間主観性に関連していると思う。相手に自分が何について思ったのか/いるのかを理解してもらう。会話分析の修復とか結び付けられてると思うんだけど、ああいう所でも見ておくとすごく間主観性ができているなと思ったりします。
川島:そうだよね。
高田:共通のものとか環境っていうのをグランドにしてインタラクションが成り立つっていう図式が大事ですよね。
マット:そうそう。何か子どもがそれを開始するってのが面白い。自分からそれを何か、「いたんだ!」とか「猫ちゃん!」とか。いきなり指差しが先、ケンドンが言ってるような動きが先で、言葉が後から「あっ」とか。だからそういう所から見ています。
川島:気づきの前ってさ、インタラクションの動きがとまって、気付きが無い状態の気付きの時もあれば、オンゴーイングであって気付きの時もあると思うんだけど、オンゴーイングの時の気付きがあったら面白いよね。
マット:そうだよね。
川島:なんで私がそれを言っているかというと、怒ったり、子どもが何か注意されたりしている時にシフトアテンションみたいな感じで、怒られているアクティビティから全然違うアクティビティに行くために「あ」みたいな。散歩していると「行っちゃだめ」とか、そういうルールみたいなものもあるだろうし、そういうものとかと絡めて研究すると面白いだろうなと思いました。
高田:ディレクティブの研究の時に。
マット:そうそう。もちろん一番大事なのは安全なので、それがガイドしているわけじゃん。それ気付くってことはもしかしたら危ないかも。「車」って言ったら車来ているかもしれない、じゃあ皆どけなきゃいけないっていうこともあるし、あとは鳥がいるとか、それは関係なくただ歩いている、安全な場所で歩いているからそれができる。「危ない、危ない!」って言ったらそういう気付きがメインアクションにならない、無視されちゃうかもしれない。あと、連鎖みたいに誰か気付いたものから開始されて、後から別の子が別のものに気付くとか、次の子が気付いて大体円みたいになっている。15分くらいなんか今度は何?みたいに。
高田:気付きの連鎖がある。
マット:気付きの連鎖みたいに、一つだけで終わってしまう場合もあるし、次から次へっていう。
川島:そこにゲーム性みたいな、お散歩の中のその楽しさの中の1つが、お互いが何か見つけごっこじゃないけどそういう包容性がある。それが連続するとそういうゲーム性があるんだけど、1つの気付き、それが単独だったらならないんだよね。
マット:そうそう、それを誰が開始するのか。大体最初は、保育士が「○○だ」と言うんだけど、それが子どもからスタートラインで大体20分くらい歩いて行くわけだから、その中で何回も何回も見られる、それが面白い。
高田:このプロジェクトとしても、まあ僕自身はずっとフィールドワークでenvironmentally coupled gesture、interactionみたいなものとか、way findingのような動きながらやるinteraction on the moveーみたいな話をしてきました。特にこのプロジェクトに関してはプロジェクトのタイトルもecological future makingってなってるんですが、狩猟採集民が定住化するときのように環境がガラッと変わった状況に注目しています。環境を利用してinteractionが進むって言うのは一般的に言えることだと思います。ただこのプロジェクトの対象社会はどこも、すごく変わってしまった環境の中で、社会が再編しないといけないような状態にありつつ、言語社会化も進んでいくような状況にあります。そこで、ほんとに動きながらのinteractionとか環境に対しての気付きは、プロジェクトとしても面白いポイントのひとつです。さっきのバングラデシュのように異言語とか異文化との出会いっていうのも、その点では面白いですね。このプロジェクトではコンタクトゾーンがキーワードになっています。主には狩猟採集民と農牧民のコンタクトに焦点をあてていますが、プロジェクトとしてはさらに広くコンタクトゾーンについて考えてみたいと思っています。異質なものが出会った時に特に子どもとか養育者っていうのがそれをどういう風に自分たちのインタラクションに取り入れて行ったり、既存のものに再編する/していったりっていうのが関心の中心です。その点では、マットが先に述べた車のデータの話も聞きたいですね。
マット:空間のとらえなおしが、大きなテーマとしてあるかなと思います。あと、アクティビティもあるじゃない、食事の時とか、遊びとか。歩いているっていうのは、活動ではなく、活動Aと活動Bの間ぐらい、traditional spaceみたいな。そういうスペースの中で間主観性を作り上げたり、結構言語社会化ができたりしているかなという気がする。だからそれは(これまでの研究では)あまりフォーカスされていない。(本プロジェクトの海外研究協力者でもある)エレノア・オックス先生たちは、食事であったり、ある開始の時だと読み聞かせの大体最初と最後のboundary activityで、眠るスペースはあんまり始まりと終わりははっきりあるんだけど、だけど少し普通のアクティビティと違う気がする。
(中略)
お世話になった先生について
山本:3人はこれまでの研究でも長らくお付き合いされていると思いますが、これまでお世話になった方などはいらっしゃいますか?
高田:この間、亡くなったEmanuel Schegloff先生ですかね。
川島:会話分析の創始者の1人のEmanuel Schegloff(2024年5月に逝去)。マットも(彼の授業)取ってたよね、一緒に。
マット:その授業で知り合ったんだ!あれ、Schegloff、怖かったんだよね、最初は。
川島:そうそう(笑)
高田:怖いけど、すごいメンターシップみたいなのがあって、やっぱりこう学んでるって感じはする。
マット:いつも宿題というか。
川島:そう。
マット:ラボに行って、データを聞いてトランスクリプションをせずに分析しないといけなかった、だからすごくトレーニングされているような。
川島:あれはすごくいいトレーニングだったよね、同じデータで。でも衝撃的だったのが、あの時でさえ30年前?1970年代くらいのデータだったのかな、materialsとしてあるのは。それをずーと、fresh!みたいな感じで。データセッションみたいな感じですると「はあ!今気付いた!」みたいなことをバーってしゃべってて。30年前に撮ったデータをそんなにフレッシュな目で見て、よくマニーとかデータセッションとかの時に「僕は先生だから、authorize to say the right things」じゃないみたいなことをすごく言ってて、誰でもデータの前では平等だからって何回も言ってるのを覚えてます。そのequalityを保ちつつ、かつ30年前からずっと見てるデータに対してfreshなobservationをその場でprovideできる、そのマニーのフレッシュな気持ちでデータに接してたマニーの偉大さを今、改めて、失いたくない部分として思い出すことがすごく多い。
(中略)
マット:マニーのレクチャーみたいなやつ、そのままだったんだよね、このまま手を使ったり。
高田:あのビデオで使ったときは、川島と僕が出席してた時で。
川島:そうそう。ビデオ撮ってた時で。多分マットの時が1年、私たちは2回か3回くらいとれって言われてて、2年目で取ってる時に明さんが来て、そのずっと後ろでずっとビデオで撮ってて。私2年目なのにまだ全然分からなくって、2回目のレクチャーでもなんでかわかんないって思ってずっと「はい!」って(挙手して)、後ろにビデオあったのにそんなの何も考えないで挙手して聞いてたの。そしたら何年か経って何かの集まりに行った時にそのレクチャーを見てた学生が「あの理恵?あの理恵??」とかって。「もしかしてあのマニーの授業で手上げてた理恵?」みたいな。
マット:あれは学部生と一緒に出てたやつだから。それもちょっとびっくりした。学部生ちょっと後ろの方に座って、我々院生が前3列くらい。
川島:そうそう。後ろの方、院生がずらーっと。
高田:でもねー。この間の(2024年6月にSeoulで開催されたThe International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysisの)パーティーの時もみんなが語る思い出が結構似てるんやなって思ってやっぱり、マニーはマニーだなって。
川島:今、先生になって、マスター書いた時とかデータのアナリシス持って行った時とか、line by lineで直されて、2時間とか1週間に1回ずつちょっとずつ持って行って書き直して書き直して・・・ってずっとやってったんだけど、あんなことマニーよくやる時間あったよね。writing もしててresearchもしてて・・・
マット:あれは多分わかんない、学生のTAの方もしてくれていたと思う。大学院生のものまでやったかどうかはわかんないけど。
川島:そう、なんか、今考えるとあんなになんで時間取ってくれたんだろう、取れたんだろうマニーはすごいなあって思う。
マット:後言わないといけないのはCharles Goodwin。もう5~6年前に亡くなって。
川島:もう本当にお世話になって。
マット:僕にとってはGoodwinの存在が大きい。4年間ずっとそこのラボに行ってたから。僕にとっては世界が変わった、っていう。
川島:あのキャラはもう、というか唯一無二というしかない。
高田:よく聞くと意外と毒舌だったりもする。
川島:時々ね(笑)結構ドライだったりする時もある。でも、非常にエンカレッジ風で。「自分のデータなんでこんなに面白いことに気付かなかったんだろう!」ってチャックがしゃべっている時は思うの。「わー!すごいね、こんなに面白い!わーー」って言ってるときは、「すごいデータなんだ!」って思うんだけど、帰ってさあいざ書こうってなると「何がおもしろいんだったっけ?なんて書きゃいいんだ!」って(笑)
マット:あの時はテープカセットとか、IC playerとかなかったから、カセット持ってきて(笑)
高田:マニーもチャックもすごい先生だけど、発想の仕組みが違うというか。チャックは色んな所にコネクトしながらまた違う所に飛んでいく感じ。マニーはすごく整理された経典がマニーの背後にある感じ気がして。その違いはすごく感じたかな。行くたびに新しい枠組みを提供してくれたり、チャック自身もそれを見つけ出したりしてるんだろうなと感じる所はありました。それにみんながアトラクトされてやってみようとするけど、自分ではなかなかできないという。
川島:そうです。
(中略)
高田:どの時代にいるか誰に会うか、って結構偶然の要素もあるけど、それによって自分の興味とかが作られていくこととかキャリアが変わってっていうことがあるから大事ですよね。出会いを大事にして研究を続けていくっていうのは。
基盤Sの発展に向けてのアドバイスをください
高田:このプロジェクトで言うと、子どもと養育者の関わりにはずっと注目しています。子どもはとくに0歳から5歳まで。日本でやってきた研究をもちろん引き継いでいるけど、それをアフリカの全然違う、学校も教室の中じゃない活動がすごい多いような環境だったりとかで見ています。そういう環境では、外にあるようなものが遊びのおもちゃになっている。もともとは、子ども向けのおもちゃじゃないものです。いまプロジェクトで取り組んでいる紙芝居なんかももともとは現地の民話です。口承の語りでみんなが受け継いできたようなものが今廃れつつあるのでそれを紙芝居にしています。産業社会とはすごく違う環境で子ども-養育者の相互行為がどうやって組織化されるのかに注目しています。みなさんから、色んな示唆をいただけたらなと思います。
川島:私がアフリカの話を聞いてて思うこと・・・
高田:川島さん一回行ったこともあるからね。
川島:(ボツワナのフィールドに)行きました(笑)なので思うんですが、社会的な変革っていうのを経験しているグループだと思うんですね。住む場所だったり、価値観だったり、仕事だったり、子育ての方法もおそらく少しずつ変わってしている中で、変化っていうものがどこで見えて、どういう風にスタートされるのか。私も色んな制度的なものが変わっていくとか、今までできなかったことができるようになってとか、そういう変革っていうものが人と人とのコミュニケーションだったり、関わりにどういう風な形で表れてくるのか、に関心を持っています。自分の(別プロジェクトで扱っている)関わり、医師と患者の関わりもどんどん変わっていっています。新しい技術などがどんどん投入されてたときにどういう説明がなされるかっていうようなことも(関心が)あるし、そういう変化みたいなものが及ぼす…どっちがどっちかはちょっとあれなんですけど。マテリアルがあるからインタラクションが変わっていくのか、インタラクションが変わったことによってマテリアルがうまく活用されているのかは、どっちが先かは分からないのですが(笑)そういう社会の変革と相互行為みたいなものは一般的に共通してデータの中で見えてくるものなのかなと思っています。この基盤Sってアクションリサーチをするっていう目的でやっているので、それって既存の物に何か新しいものを導入するっていうことが目標になっていると思います。そういう変革だったり変化を促すっていうことが、相互行為を観ることでスムーズにうまくいくやり方みたいなのもあるんじゃないかと思っていて。社会がかわるきっかけっていうのは、私は、コミュニケーションから変わっていくと思っているんです。なので、その変革みたいなものがどこに表れていくのかっていうものは、今後はアクションリサーチをしていく中で、何かアイテムがイントロデュースされたり、されるようにうまく整えるみたいなやり方の中に、そういうコミュニケーションの研究が生かされていけばいいなっていう、そういうような研究がどんどん広がって行ったらいいなっていう気はしています。
高田:マットとの関連で言うと、Language Socializationはこのプロジェクトでも重要な理論的な軸です。たとえば、(Language Socialization研究を推進してきた)エレノアたちが言っているmicro-habitatっていうのは申請書の段階から中心概念のひとつに位置づけています。規模は違うけど、日本に比べれば自然環境の中に目に見える形で出来上がっている村みたいな所を対象にして、その中で起こっている言語社会化って言うのを環境と関連付けた形でみながら、その中で彼ら・彼女らのhabitusがどうやって出来上がってきているのかっていうことを考えたいっていうことが基本アイディアです。日本で考えたことが砂漠や熱帯林の環境の中でどういう形をとっているのか、日本と似たような形があるのか/無いのかっていうのは考えられるのではないかなと思っています。それこそ、動物とか植物との関わりっていうのは、日本の特色ってのもあるだろうけど、アフリカ狩猟採集民や牧畜民の特徴っていうのも面白いでしょう。
マット:共通点と相違点というか、アフリカと日本の共通点は何なのかとか、そういうのも。例えばstory tellingのテーマでいくつかの日本だけでなく、中国とかアメリカとかアフリカとかどうなってんのかっていう共通点を、人類の中でこう文化とか違うんだけどもstory tellingはstory tellingという構造があったり、参加の仕方があったりとか、そういうのをやっていくと面白いと思う。そういう共通点を見つけ出すというのが面白いなと思います。今、日本もそうだけどテクノロジーとかスマホとか子どもでも持ってるので、アフリカはどうなってるのか、変わってどうコミュニケーションしてるのかとか。相違点はいっぱいあると思うので、共通点は何かとか。アフリカとかスマホとか子どもどう?
高田:(アフリカでは)スマホは割と早く導入されてます。
マット:じゃあそこから共通点が見えてくる(笑)
高田:あと、チャックが言う、environmentally coupled gestureっていうのはまさに、環境の中で色んなinteractionをしている、たとえばカラハリの環境の中で野生動植物を求めて移動して、それを食べてっていう生活をしている人なので、アメリカのデータや日本のデータを見るより、より切れ味するどく使えるなと思っています。チャックのメモリアルの論文集では、僕はその概念を使って論文を書いたのですが、そういう意味では色んな発想が繋がる考察のポイントになりますよね。
マット:僕ら何年か前に子どもが泣くことについて特集出してて、ニュージ-ランドとかスウェーデンとか日本とか、そういう特集とか(をこのプロジェクトでも組んだりすると)学ぶことが多いなって気がする。泣くっていうその普遍的なことなんだけど、どの社会でも対応の仕方がやっぱり文化によってちょっと変わったりすることもあるし、でも共通点がいっぱいあるので、じゃあそれは何なのかとかを考える必要があるなあと(思います)。言語形式もまあマックス・プランク研究所でもクエスチョンとかいろんな言語の観点で比較研究をやってたけど、我々に何ができるか。文法形式とかだけでなく、違うアクティビティ(を比較する)とかそういう観点からがいいかなと思います。story tellingも1つの代表的なものではあるけど、散歩とか食事とか色々なアクティビティがあると思うのでそこから何が言えるのか。もちろん会話分析の手法を使って。会話分析を使わないとミクロなレベルでは何も言えないと思うので。それはメゾレベルとマクロレベルで言ってるのか、アイデンティティの形成とかルールとかモラリティとかとどう関係しているのか。それらを通じて、会話分析を越えた研究を目指せるといいですね。
高田:ありがとうございます。
マット:会話分析を大事にしながら、でもメゾレベルとかマクロレベルでもう少し大きなことが言えるのではないか。人類とは何かというところを。
川島:でもそういう人類の共通点みたいな、human natureというか、インタラクションの中に見えるそういうエッセンスが何か見えたら楽しいなと私は思う。違いを語るのもいいけど、共通点を語ることで、what we areという所がもう少し見えたら、マニーが言ってるようなニューヨークからカリフォルニアへの一歩のそのもうちょっと先みたいな(笑)
高田:逆じゃないの?(笑)
川島:逆?あれ逆?ニューヨークからカリフォルニアじゃなかった?なんか、「(会話分析の研究の展開において)僕たちはニューヨークからカリフォルニアへの第一歩を踏み出したに過ぎない!」ってずっとレクチャーで言っててさ、第二歩目は何だ?シークエンス・オーガニゼーション(Manny Schegloffの代表的な著書)の次?みたいに思ってたけど(笑)でもそういうような、次に繋がるような仕事ができたらいいですよね。