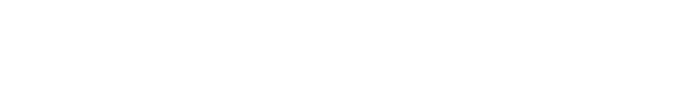タンザニア派遣報告
京都大学大学院
アジア・アフリカ地域研究研究科・助教
齋藤 美保
2025年2月11日から3月23日までタンザニアに渡航し、おもにカタヴィ国立公園周辺で現地調査を行った。現地調査では、「アフリカ狩猟採集民・農牧民のコンタクトゾーンにおける行動生態学的調査」の一環として、当該国立公園周辺に位置する3つの村をめぐり、各村において野生動物による食害に関するインタビュー調査を行った。本インタビューでは、村人の野生動物に関する知識と動物観を明らかにすることを目的とした。本報告書では触れないが、これらの結果を南アフリカで同様に実施したインタビュー結果と比較することを最終的な目標としている。同様に本報告書では触れないが、レンジャーと村人の社会関係についても考察することを目的としていたため、タンザニアでは、3村を2カテゴリーに分け(①国立公園オフィスに最も近く、また公園に勤務するレンジャーも居住する村、②国立公園境界に隣接するが国立公園オフィスからは遠く、またレンジャーとの関りはほとんどない村)、各カテゴリーでそれぞれ60人以上インタビュー調査を行った。グループ①はもともとはピンブエやフィパといった民族で構成されていた村だが、現在は多様な民族で構成されている。一方グループ②は主に半農半牧を営むスクマの人々が暮らしている。タンザニアでは国立公園と村の境界に柵はなく、人が公園内に許可なしに入ることは制限されている一方、野生動物が公園外に出てくることはある。
インタビューでは、当該村での居住年数、職業、農地や住居周辺で観察される野生動物種、その野生動物が公園外にやってくる目的、野生動物に対する印象、野生動物との軋轢を防ぐために必要と思われる対策、レンジャーあるいは村人への印象、などを聞き取った。
インタビューの結果、①グループの人々の居住年数は②グループの人々のそれよりも長く、特に②グループではここ数年で移住してきた人が目立った。その年数の違いが影響しているのか、②グループではとくに女性で「野生動物が怖い」という回答をする人が①グループよりも多かった。一方で、「移住してきた当初は野生動物のことがわからず怖かったが、3年たった今はもう慣れた」と回答する人もいた。公園外で遭遇する野生動物種について尋ねたところ、両グループ共通して一番初めに「ゾウ」と答える人がほとんどであった。そのあとは、カバ、バッファロー、キリン、インパラなどの回答が続いた。

その後の様々な質問項目に関して、興味深い回答が複数得られたが、今回はそのうちの2つのトピックに絞って報告したい。一つ目に、野生動物に関する印象を訪ねると、多くの村人が食害にあっているにもかかわらず、野生動物を嫌悪している答えはほとんどなかった。多くの人が、「野生動物はタンザニアの自然の一部(あるいは、神様が創造したもの)であるから、野生動物は好きだ」と答えていた。ただしその後には「ただ、公園外に出てきて我々の食料を奪うのはどうにかしてほしい」との回答が続いた。つまり、確かに彼らは野生動物との軋轢を抱えて、それを認識しているにもかかわらず、完全に嫌悪するには至っていなかった。その理由として、野生動物を「神様の創造物」として認識している、あるいは「タンザニアの他の場所ではこんなに野生動物を見ることはできないし、野生動物を自分の目で見ることができるのは嬉しい」といったような野生動物の「価値」の認識が背景となり、野生動物の存在を許容している印象を受けた。また二つ目に印象的だったトピックとして、野生動物と人間という単純な二元論に落とし込むのではなく、「野生動物と人間は似ている」と語る人も度々みうけられた。その野生動物としてゾウがよくあげられ、「ゾウは人間のように賢いから(農地に入ってきた時に)追い払うのは大変だ」、「人間のようにゾウは地面に落ちたマンゴーは食べない」、「ゾウは人間のように乳房がお腹の前の方についている(報告者からの補足:ウシやヤギは後ろ足の付け根に乳房があるが、ゾウは前脚の付け根にある)」といった回答が得られた。ここから、食害を受けながらも、村人は興味関心をもって隣人である野生動物に接している様子がうかがえた。

調査終了後、ニェレレ国立公園に移動し、国立公園に勤務している生態学者のマナセ博士と研究打ち合わせを行った。ニェレレ国立公園はタンザニア南東部に位置し、報告者のおもな調査地であるカタヴィ国立公園同様ゾウなどによる食害被害が報告されている。同じ南部で活動する研究者として今後の共同研究の可能性について意見交換を行うことができた。

その後ダルエスサラームに移動し、アルディ大学ではコンバ研究員、ダルエスサラーム大学ではジャッソン講師と研究に関する打ち合わせを行った。とくにコンバ研究員は、人と野生動物の軋轢に強い関心を持っている。コンバ研究員は来年度来日予定で、来日までに収集するデータおよび来日後に実施するデータ分析などについて議論した。今後、人と野生動物の軋轢に関する共同研究を円滑に進めることができることを確認した。
今後は論文化や学会での発表を念頭に、データの分析及び考察を進めていく。また本渡航に際し、ご支援くださった皆様に感謝申し上げます。